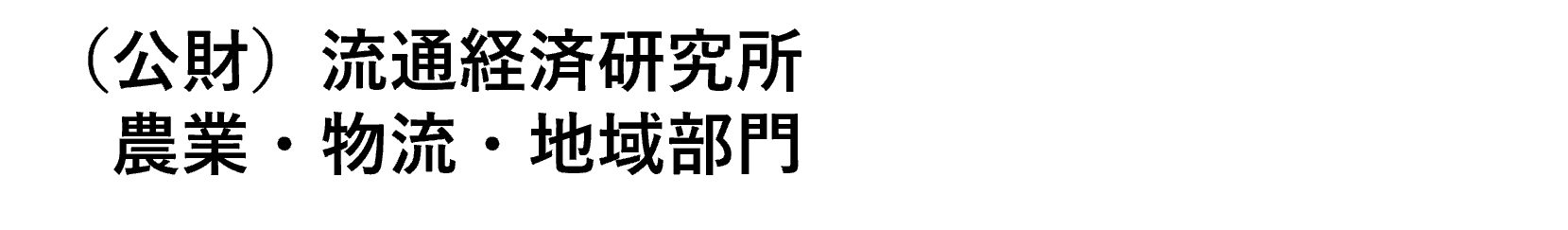公益財団法人流通経済研究所
研究員 渡邊 秀介
東京にある熊本のアンテナショップ「銀座熊本館」に連日行列ができていることが報道されている。もちろんこれは、先日発生した熊本地震の被害に対して、遠隔地からできる支援として、地元産品の購入と募金のために訪れる人々の行列である。この興味深いできごとは、東日本大震災以降に人々の間で深化/進化した被災地支援のありかたの表出であると同時に、アンテナショップという存在が普段どう認知されているのかをも示しているように思われる。
「募金の窓口として熊本のアンテナショップを選ぶ」という行動は、来店者が「アンテナショップ≒現地」 と捉えていることの証左だろう。募金経路が複雑化した現在、募金が適正に被災者に届けられるかどうかは、寄付者にとって重大な関心事である。さまざまな支援方法の中から(最もコストのかかるはずの)ボランティアという形態を選ぶ人が多いことからも分かるように、人々には自らの善意をより直接被災者に届けたいという心理があり、ゆえに募金の際には、募金経路上にブラックボックスがあることを避けるインセンティブが働く。これを踏まえると、おそらく最寄りの小売店でも同様の募金活動がなされている中で、あえて銀座のアンテナショップが選ばれるのは、そのお店がより直接にその地域とつながっていると感じられているから、ということになるだろう。その意味で、東京の来店者にとっては、アンテナショップは単に物珍しいお店というだけでなく、文字通りその地域の「飛び地」として観念されているのである。
地域活性化(ないし復興)が広く叫ばれる中で、その拠点として地元産品を扱う店舗(アンテナショップ、あるいは道の駅や産直施設も同様かもしれない)は、販路拡大ないし地産地消のための商業施設というだけでなく、その地域の人と文化を代表する施設とみなされるようになってきている。2014・15年に全国モデルに選定された道の駅6駅も、地域が売り出したい商品、力を入れている領域、訴求したい魅力を十二分に発信できているからこそ評価されたものだろう。このような施設が外部の人との結びつきを強めることができれば、それがそのまま地域全体と外部の心理的距離を縮めることになる。地域代表となることをより意識した施設づくりが、今回の募金のように、遠隔地の人々と当該地域とのつながりを強め、ひいては実際の人の流れとなって、本当の「地方活性化」へとつながっていくのではないだろうか。